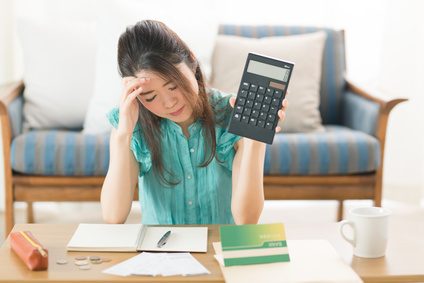昨今のアパート・マンション投資ブームに伴い、サブリース契約の件数が増加しています。空室リスクを回避できる家賃保証のメリットがある反面、「十分な利益を得られない」「解約時に多額の違約金を請求される」などでサブリース業者との間でトラブルになる事例も増えています。
今回は、そんなサブリース契約の実態とリスクについて、家賃保証の矛盾と契約解約の難しさ、そして売却価格は相場より2割安くなるという3つの視点から紹介します。
これからサブリース契約を検討している方は是非参考にしてください。
サブリース契約のメリットは空室リスクがないこと
そもそもサブリース契約(家賃保証付き一括借上)とは、サブリース業者が不動産オーナーから賃貸物件を一括で借上げ、第三者に転貸し、賃料の差額で利益を稼ぐビジネスモデルです。
不動産オーナーにとっては、保証される家賃は近隣相場の20%〜30%割引いた金額になりますが、空室戸数に関わらず、サブリース業者から毎月一定の家賃が支払われるため、安定した賃貸経営を行うことができます。
空室リスクをサブリース業者が負担してくれるので、何となく不動産オーナーに有利な様に感じられますが、実態はそうでもありません。不動産オーナーにとっても確実にリスクは存在します。
サブリース契約のリスクは4つ
リスク1. 家賃減額は避けられない!?
1つ目はサブリース業者から必ずと言っていいほど要求される家賃保証の減額です。
「サブリース契約時に月額家賃100万円を10年間保証するとサブリース会社から説明されたのに数年後に半分の50万円に減額されてしまった」というような事例をよく耳にします。
一見すると、常識的に考えてサブリース会社の契約違反だと思いますよね?しかし、実際はそう簡単な話ではありません。
通常、不動産オーナーとサブリース業者が締結するサブリース契約は「普通借家契約」が適用されます。
この普通借家契約は借主有利となっており、仮に契約書に「一定期間は借主であるサブリース業者から賃料の減額請求はできない」という様な条文が特記されていても、実は減額請求はできてしまいます。これは普通借家契約の強行法規といわれる規定によるもので、上記の様な特約は無効となってしまうからです。
かなり矛盾があるサブリース契約の内容ですが、今後、借地借家法の改正などが起きない限り、要するにサブリース業者が謳っている固定の家賃保証は実は保証されていないということです。
しかも現在のように家賃が上がっている状況でも、築年数や設備劣化などの理由で家賃保証が減額されてしまう可能性もあります。(不動産オーナーが気付かないところで家賃を上げて、サブリース業者の懐だけが潤うと言う最悪のパターンも考えられます。)
この家賃保証と減額請求可能の矛盾が原因で、不動産オーナーとサブリース業者間でトラブルに発展することが多いようです。
リスク2. サブリース契約を解約するのは至難の技!?
続いて2つ目のリスクは、サブリース契約を解約する場合は正当事由が必須であるということです。
普通借家契約は借主有利の契約であることは既に紹介しました。
借主が個人でも不動産業者であっても借主保護に変わりません。サブリース契約締結後、内容に不満があったので不動産オーナーからサブリース業者に解約の申し出をしたとします。
しかし、例によって普通借家契約では、貸主である不動産オーナーから解約の申し出をする場合は、正当事由が必要です。しかも正当な事由に該当したとしても、必ずしも解約が認められるとは限らないため、貸主からの一方的な解約はほぼ不可能と思っていた方が良いでしょう。
なお、代表的な正当事由には以下のようなものが挙げられます。
- オーナー自身・親族が建物に居住する必要がある
- 旧耐震基準の物件で、老朽化にともない建物を建て替える必要がある
- 再開発事業や公共工事により物件を売却する必要がある
- オーナーの金銭的な理由により物件を売却する必要がある
- 長期にわたり借主側から賃料を受け取れていない
仮に解約をサブリース業者が認めた場合でも立退料、もしくはそれに準ずる違約金を支払わなければならないケースがあります。サブリース解約時の違約金の相場は契約内容によって異なりますが、一般的には月額賃料の6~12カ月程度が相場です。
リスク3.想定外の高額な工事費用を請求される
サブリース物件では、賃貸管理は全てサブリース業者が行います。そのため、不動産オーナーは管理の手間はかかりません。
空室が続いていたり、設備が古くなった場合は、リフォームをしたり設備を交換するなどの工事を行う場合もあります。これらの工事内容によっては、不動産オーナーに一部請求される場合もあります。
あまりに長期期間空室が続くと、サブリース業者が潰れてしまうと言うリスクもあるので、物件価値を維持・向上するために工事はある程度必要ではありますが、想定以上の工事費用を請求されてしまい、トラブルになる場合があります。
あらかじめ、サブリース契約に何が含まれているか、工事が必要な場合の手続きの流れなどを確認しておくことが必要です。
リスク4. 売却価格は相場より2割安くなる?
一般的にサブリース物件は売りにくいです。理由は上記2つ「家賃減額は避けられない」「サブリース契約を解約するのは至難の技」の中でも、特に解約が難しいことが絡んでいます。
そのため、いずれ売却したいと思った際には、サブリース物件は投資用物件相場より2割ほど安い価格となってしまう可能性があります。しかも売却金額だけでなく、売却期間に影響する場合もあります。
目先の安定収入だけにとらわれず、出口戦略まで見据えて判断することが大切です。
サブリース契約以外の投資用物件管理の手間の減らし方
サブリース契約では家賃収入が保証されるだけでなく、賃貸管理の手間が減らせるというメリットもあります。そして賃貸管理の手間を減らす方法は、サブリースの他にも「管理委託」があります。
サブリースではオーナーがサブリース会社と賃貸借契約を結び、サブリース会社が物件を又貸しする形式です。入居率に関わらず一定の賃料が保証される一方で、賃貸経営の決定権はなく、礼金や更新料の収入は得られません。また解約時には高額な違約金が発生する可能性があります。
これに対し管理委託は、賃貸経営の主権をオーナーが保持したまま管理業務のみを委託する方式です。家賃保証はないため収入は入居率に応じて変動しますが、委託手数料はサブリースより低く、入居率が高ければより多くの収入を得られます。委託手数料の目安はサブリースが家賃の10~20%に対し、管理委託は家賃の5%程度です。
さらに更新料や礼金もオーナーの収入となるため、サブリースと比較して全体的に高収入を期待できる特徴があります。
ちなみに賃貸管理とは、入居者を募集するためにSUUMOやHOME’Sに広告を出したり、家賃滞納があったら取立てを行う、入居者からの問い合わせ対応、退去後の原状回復などを行います。自分で賃貸管理をするのが難しい方は、サブリースだけでなく管理委託も併せて検討してみるといいでしょう。
サブリース契約締結前の確認が大事!
今回は、サブリース契約の実態とリスクについて、家賃保証の矛盾と契約解約の難しさ、想定外の工事費用請求、売却価格が安くなるという4つの視点から紹介しました。
もうお気づきかと思いますが、サブリース契約を締結してからこのようなリスクに気づいても手遅れなケースがほとんどです。
不動産投資は大きなお金が動くビジネスです。サブリース契約も20年、30年と長期間の契約になりますので、しっかりとした事前準備、リスクの把握が肝要です。